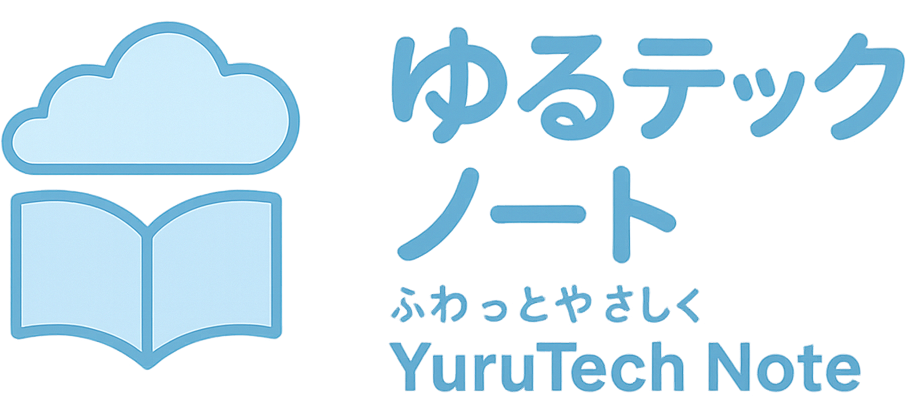ハッシュ値とは?
ハッシュ関数は、任意の長さのデータから固定長のハッシュ値を生成する一方向関数で、情報セキュリティやデータ検証に広く使われます。
🔐 ハッシュ関数の基本
ハッシュ関数は、入力データを不可逆な固定長の値(ハッシュ値)に変換する関数で、同じ入力に対して常に同じ出力を返します。
ハッシュ関数の特徴
以下はハッシュ関数が持つ典型的な性質です。
- 📌 一方向性:ハッシュ値から元のデータを復元することは非常に困難です。
- 📌 衝突耐性:異なる入力から同じハッシュ値が得られる確率が極めて低いことが理想です。
- 📌 拡張不可性:入力をわずかに変更するだけで、まったく異なるハッシュ値になります。
🧮 代表的なハッシュアルゴリズム
現在利用されている主なハッシュ関数を以下に示します。
MD5
高速なアルゴリズムとして広く使われていましたが、衝突が容易に発見されるようになり、現在ではセキュリティ用途には不適です。
SHA-1
かつてSSL証明書などでも使われていましたが、Googleにより現実的な衝突が証明されたため、現在は非推奨となっています。
SHA-2(SHA-256 など)
現在主流のアルゴリズムで、電子署名やTLS、ブロックチェーンなどに使用されるなど、信頼性の高い手法とされています。
SHA-3
Keccakという新しい構造に基づいたアルゴリズムで、SHA-2とは異なる内部設計を持ち、耐性と柔軟性に優れています。
🛡️ パスワード保存とセキュリティ
パスワード保存にハッシュを使う場合、ソルトとストレッチングを併用することで安全性が高まります。
ソルトとストレッチング
パスワードハッシュには以下のような追加対策が推奨されます。
- 🔑 ソルト:同じパスワードでもユーザーごとに異なるハッシュ値にするためのランダムデータ。
- 🔑 ストレッチング:ハッシュ処理を複数回繰り返して、総当たり攻撃に対して強くする手法。
- 🔑 推奨アルゴリズム:PBKDF2, bcrypt, scrypt, argon2 などが業界で広く推奨されています。
💼 主な用途
ハッシュ関数は多くの実用的な目的で使われています。
用途一覧
- ✔️ ファイル整合性チェック:ダウンロードや転送時にファイルが改ざんされていないか確認できます。
- ✔️ HMACによる認証:共有鍵と組み合わせて、送信されたメッセージが改ざんされていないかを確認します。
- ✔️ ブロックチェーン:各ブロックの整合性とチェーン構造を保つためにハッシュが利用されます。
- ✔️ パスワード保存:漏洩してもすぐに解析されないよう、ソルトと安全なハッシュ方式で保管します。